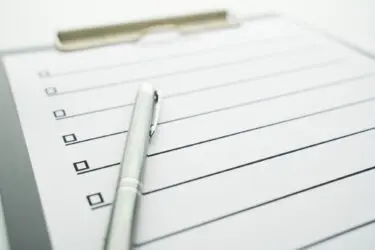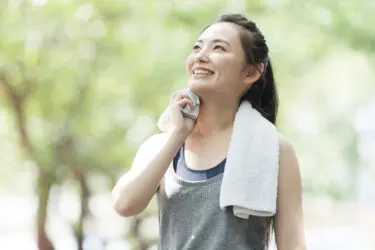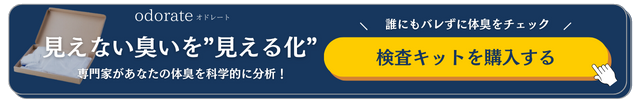体臭の原因は食生活や生活習慣だけではありません。
衣類やハンドタオルに棲みついた常在菌が体に移り、原因物質として臭いを放つことも多いのです。
しっかりと洗濯したつもりでも「生乾きのような臭いがする」場合には、衣類やタオルに常在菌が残っていて悪さをしている可能性があります。
また、服の生乾き臭が体臭と混ざり合って、さらにいやな臭いとなる可能性も。
生乾き臭の防止と服の生乾き対策として、衣類の洗濯・乾燥方法を一度見直し、体臭対策してみましょう。
▼体臭の臭いの種類に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
ご自身の体臭の種類が、どのやタイプに該当するかご存知でしょうか? 例えば、「チーズのような臭いを感じるけれど、これはどんな体臭なんだろう?その原因や対策方法は?」というように、ご自身の体臭がどんな種類かわからないという方もいらっしゃること[…]
生乾き臭が発生するメカニズム
洗濯後に発生する衣類の悪臭は、衣類の繊維にこびりついた細菌のしわざであることがわかっています。
主にモラクセラ菌(モラクセラ・オスロエンシス)という常在菌が繁殖する際に、4-メチル-3-ヘキセン酸という不快な臭いの原因物質を発生させているのです。
衣類に残存した皮脂汚れと高い湿度、細菌が繁殖しやすい温度などの条件が整うと、あの使い古した雑巾のような悪臭を放つようになります。
しっかり洗浄・天日干しても臭いの原因菌は残る
長い間使用しているタオルや衣類などは、やがて繊維が傷み、その劣化部分にモラクセラ菌が忍び込んでがっちりと繊維にからみつき、洗っても簡単には落ちなくなってしまいます。
そして、再び菌が活動しやすい環境になれば増殖します。
「生乾き」に「体臭」が加わると臭いが強くなる
ワキガ体質や臭いが強い体質など、体臭が強い人は、衣類にその原因菌を移すこともあるので、注意が必要です。
洗浄・乾燥の仕方が不十分だと、生乾き臭が体臭に加わって、ダブルの不快臭となるリスクがあります。
体臭対策「生乾き臭」を防止するポイント
洗濯槽の中をいつもキレイに
まずは洗濯機の中で洗い落とされた細菌やカビが繁殖しないよう、定期的に洗濯槽の汚れを落としてください。
月に1回が理想ですが、忙しくても3ヵ月ごとに洗濯槽専用のクリーナーや重曹を使ってクリーニングすれば、それだけの効果はあります。
また、洗濯が終わったら時間をおかずに洗濯物を取り出して、洗濯機のフタを開けておくと細菌の繁殖を防ぐことができます。
洗い方や洗剤を見直してみる
一度に洗おうとして洗濯物をつめ込んでしまうと、洗浄・すすぎがうまくいかずに細菌が洗い落とせなくなります。
適量を守って複数回に分けて洗濯をしましょう。
洗剤では、部屋干し用の洗剤にも多く使われている酸素系漂白剤(過炭化ナトリウム)を選びましょう。
塩素系漂白剤よりも漂白作用が弱いので、繊維を傷めずに繊維の奥まで染み込んでしまった皮脂汚れを洗い落とすことができます。
風呂の残り湯を使わない
残り湯は、体から洗い落とされた細菌が多く含まれています。
それで洗濯するのでは意味がありません。
新しい水道水で洗浄するのが賢明です。
干す際も注意が必要
干すときも注意点やひと工夫が必要です。
洗濯後に濡れたままの衣類を洗濯カゴに入れていると、そこでモラクセラ菌の繁殖を許してしまいます。
洗濯が終わったら放置せず、すぐ干すことを心掛けてください。
また、洗濯カゴも定期的に洗って清潔にしておくことが肝要です。
乾燥の仕方は天日干しが望ましいのですが、もし部屋干しなら、できるだけ風通しの良い場所を選ぶようにしましょう。
それが無理なら扇風機やエアコンを除湿モードにし、洗濯物に風を送って早く乾かすようにすれば、細菌の増殖を抑えることができます。
高温に弱い性質を利用する
もう一つ、熱に弱い細菌の性質を利用して、熱いお湯でつけ置き洗いする方法もあります。
40度程度では効果はないのですが、60度となると、ほとんどの細菌が死滅するためです。
ただし、日本の洗濯機は高温で使用する設計にはなっていません。
ですが、脱水後にアイロンがけをして細菌を死滅させる方法があります。
アイロンは蒸気を出さず、150から200度くらいの温度でかけて衣類全体をまんべんなく乾かすようにします。
これにより細菌を死滅させることができます。
また脱水後に、高温の乾燥機に入れて乾かす方法もかなりの効果が期待できます。
「生乾き」体臭対策まとめ
生乾き臭は、体臭そのものから発生するものではなく、身につけている衣類から発生することがおわかりになったことでしょう。
生乾き臭がする場合には、今回紹介した対策を試してみてください。
ただ、洗濯方法や干し方を変えても生乾き臭が改善しない場合は、処分することも検討したほうがいいでしょう。
▼体臭の臭いの種類に関して詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。
ご自身の体臭の種類が、どのやタイプに該当するかご存知でしょうか? 例えば、「チーズのような臭いを感じるけれど、これはどんな体臭なんだろう?その原因や対策方法は?」というように、ご自身の体臭がどんな種類かわからないという方もいらっしゃること[…]
▼体臭に関して幅広く知りたい方は以下の記事もご覧ください。
「体臭に関する記事はネット上に沢山あって、どれも似た内容だけど、微妙に内容が違う。どの情報が正しいのかわからない...」と思ったことはありませんか? そのような方に向けてこの記事を書きました。 当サイト、体臭ラボは、運営会社独自の体臭評価[…]